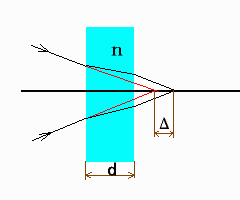
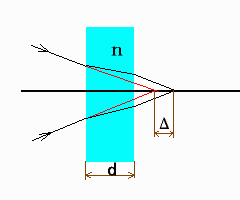
上の図で、平行平面板を入れる前には赤色で示したような光路であった光線が、 平行平面板を入れた後には、屈折して、黒色で示したような光路になり、 結像位置がΔだけ後ろに移動します。 平行平面板の屈折率をn、厚みをdとすると、この移動量Δは、 Δ=d(1−1/n) で計算できます。
例えば、屈折率1.5、厚み2mmの平行平面板を入れた場合の像点移動量は Δ=2mm x(1−1/1.5)=0.667mm となります。 厚さ2mmのフィルタを 入れたときと抜いたときでは像点の位置がこれだけ変わります。
屈折率nは波長によって異なるので、厳密には色収差も出ます。
例えば、BK7相当の光学ガラスで厚みが2mmの場合、
g線(435nm):Δ=2mm x(1−1/1.526)=0.689mm
d線(587nm):Δ=2mm x(1−1/1.516)=0.681mm
C線(656nm):Δ=2mm x(1−1/1.514)=0.679mm
となって、g線とC線の間の軸上色収差が0.010mm発生します。
R,G,Bとフィルタを交換して撮影する場合、フィルタの厚み誤差に 相当する分の像点移動があります。例えばフィルタの厚みの仕様が2mm±0.2mm とすると、複数個のフィルタの厚みの違いは最大0.4mmです。 この場合には、(n=1.5とすると)フィルタ交換によって、最大0.4x(1-1/1.5)=0.133mm の像点移動が起こる可能性があります。
尚、以上は光軸近傍で且つ光線の角度が非常に小さい場合に関する話です。 画角が小さくF数が大きい場合は、上記の像点移動だけで済みますが、例えばF数が小さくなってくると、 平行平面板による球面収差が無視できない量になってきます。
平行平面板による球面収差の量(光軸に沿って測った量)は、近似的(3次収差)に ((n2−1)/n3) * (d/8F2)程度に なるようです(参考:久保田広著「光学」)。ここで、Fは光学系のF数(Fナンバー)です。 n=1.5の場合は、(n2−1)/n3=0.370なので、球面収差は 0.370 *(d/8F2)となり、厚みが2mmの平行平面板の場合は、 F/1で0.0925mm、F/4で0.0058mm、F/10で0.0009mmとなります。但し、これらはオーダーを知るための 概略値で、正確には光線追跡で求める必要があると思います。
このようにF数が小さくなると、平行平面板で発生する球面収差が急激に大きくなります。 このため、F数の小さい(NAの大きい)生物顕微鏡用対物レンズやCD用対物レンズなどは所定の厚みの平行平面板(カバーガラスやCD)を 入れて使用したときに収差が小さくなるように設計されています。
以上は、収束する光路中(例えば、望遠鏡より後ろでCCDチップより前)に平行平面板を入れたとき の話です。カメラレンズのフィルタのように望遠鏡の前に平行平面板を入れた場合には、光軸上での像点移動・ 球面収差・軸上色収差は発生しませんが、対物レンズ並みの面精度と大きな直径の、高価な平行平面板が必要に なり、ゴースト等も発生しやすいので、(小口径機以外では)あまり現実的ではないように思います。太陽観測用の望遠鏡先端につけるフィルターなどが このタイプですね。