一言で言えば、これも、光が波の性質を持つからにほかなりません。 今回これを詳細かつ分かり易く説明したいと思っていたのですが、結局は専門書と同じ式の羅列になってしまい、 私には困難であることが判明したため詳しい解説は省かざるを得ませんのでご了承ください。 (厳密な、詳しい説明は、「ボルン、ウォルフ著:光学の原理Ⅱ、(東海大学出版会)」 などに載っていますので、難解な部分もありますが、興味のある方はご参照ください。本ページの内容もほぼこの本を反映しています。)
1818年、フレネル(Fresnel)は、このホイヘンスの原理に、2次波が互いに干渉するという条件を加えることにより、 回折現象を説明できることを、初めて示しました。(ホイヘンス-フレネルの原理)。
1882年、キルヒホッフ(Kirchhoff)は、ホイヘンス-フレネルの原理に数学的な基礎を与えました(キルヒホッフの回折理論)。
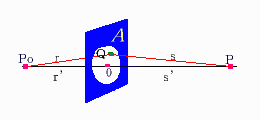
また、λは波長、A は光の振幅の程度を表す比例定数、r’は光源P0と定点Oとの間隔、 s’は定点Oと観測点Pとの間隔です。r’とs’は定数となります。
それに対してr、sは変数で、積分時に点Qが開口A の内部を移動すると変化します。 kは波数で、k=2π/λ の関係があります。
被積分関数である eik(r+s) = ei2π(r+s)/λ という 関数は、r+s が 波長λだけ変化しただけで、複素平面上で原点の回りを一回転してしまうような周期関数です。 積分時に点Qが開口A の内部を移動すると、r+sの値は、条件にもよりますが、波長λの何千倍・何万倍も変わりますので、 複素平面上で原点の回りを何千回・何万回も回転することになります。実数で例えると、積分中にこの関数は、+1と-1の間を 何千回・何万回も振動することになります(r+sの値が波長λだけ変わっただけで、+1 → -1 → +1 と一回振動する)。 従って、この式をまともに数値積分すると、計算の仕方を十分に工夫して(例えば、r+sの変化が波長に比べて十分小さな値になるように刻み幅を設定して) 計算しないと、誤差が累積して、計算したい値が誤差に埋もれてしまいます。
これを回避するためにrとsを級数に展開して、開口内の点Qの座標を(ξ,η)、光源P0の座標を(xo,yo)、観測点Pの座標を(x,y)、方向余弦(lo,mo)=(-xo/r',-yo/r')、(l,m)=(x/s',y/s')として(23)式を変形すると、
(28)式の積分記号の前は定数なので、積分の中の関数fの次数によって、積分の難しさが決まります。
f(ξ,η)として、ξ,ηの2次の項が無視でき1次の項まで採用すればよい場合をフラウンホーファ回折(Fraunhofer diffraction)、ξ,ηの2次の項が無視できない場合をフレネル回折(Fresnel diffraction)
と呼んでいます。
((注):尚、ここまでの話では、レンズはいっさい考えていません。開口(穴の開いたスクリーン)での回折のみを考えてきた訳です。)
さて、それでは天体望遠鏡の焦点面での回折像はどうかというと、光源(天体)については無限遠の距離にあるので
r'=∞つまり1/r'=0、観測点については無収差レンズの焦点面ですが、これはレンズを除いたときの無限遠観測点と等価の効果ため、
s'=∞つまり1/s'=0も成り立ち、(31)式はξ,ηの2次の項が無視でき、f(ξ,η)=(lo-l)ξ+(mo-m)η となって、焦点面ではフラウンホーファ回折像が観察されます。
(開口による回折によって無限遠にできる回折像が、レンズを入れるとその焦点面で観察される)
(lo,mo)は望遠鏡に入射する光線の方向(余弦)で、(l,m)は回折される方向(余弦)なので、 この差(方向の差、角度の差)を見る必要があります。 そこで,p=l-lo, q=m-mo として、方向(余弦)p,qで回折光の方向を表します。 もし、光軸上に天体の中心を合わせるならば、p,q が光軸を基準とした回折光の方向(余弦)そのものを表します。
以上より、天体望遠鏡の焦点面で観察されるフラウンホーファ回折像の振幅分布U(P)は、
長くなりましたので、ここで一旦打ち切ります。回折リングにはまだ到達しませんね。
次回に続きます。