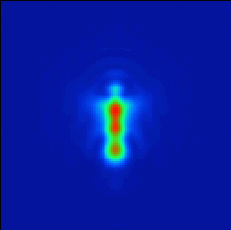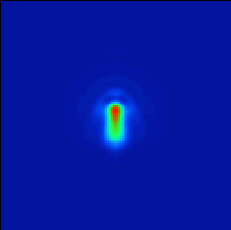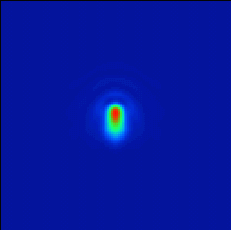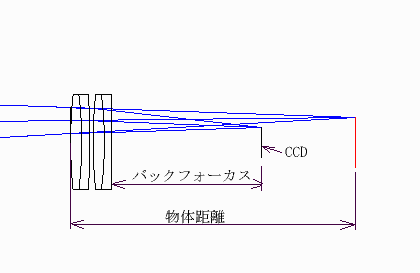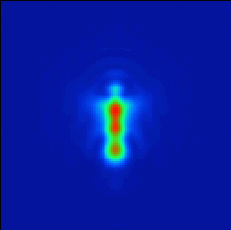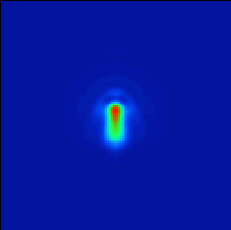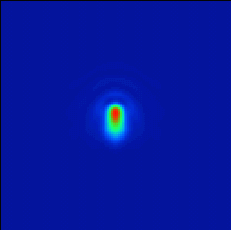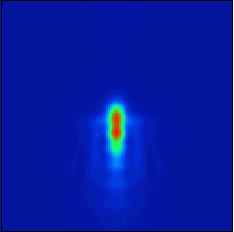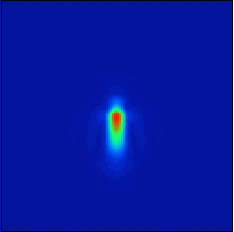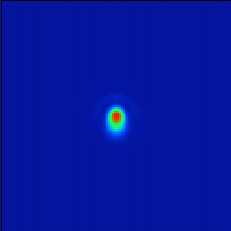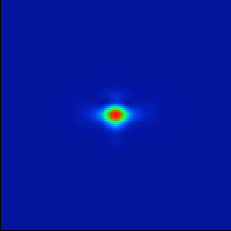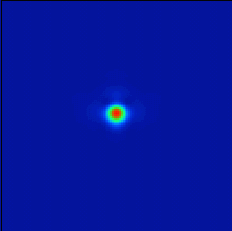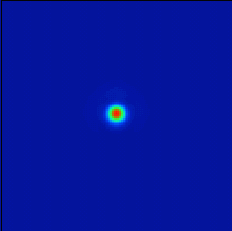レデューサー使用時のガイドチップ上の星像
(お知らせ:2002/09/22)
以下は望遠鏡の収差がゼロ(色収差もコマも像面湾曲もゼロ)という近似をしているので、
実際には望遠鏡の収差の分だけずれてしまうことをご了解ください。
望遠鏡の収差は、望遠鏡のタイプによって異なります。
シュミットカセグレンの星像とそれにレデューサーを付けたときの星像は、
望遠鏡のページに載せましたのでそちらをご覧ください。
ST-7/8(E)+レデューサーで、ガイドチップ上の星像がどのような形になるかをシミュレートしてみました。
仮定した望遠鏡
F11とし、収差はないものとしました。
仮定したレデューサー
セレストロンやミードの0.63倍のレデューサーを評価したかったのですが、設計値が分からないので、
ここでは、直径50mm 焦点距離約450mmの普通のアクロマートレンズを2個並べたもの(合成焦点距離227mm)
で代用しました。本物のレデューサーとは収差補正の具合も焦点距離も異なると思いますので、精密な評価
ではなく、大体の傾向を知ることを目的としました。
シミュレーション方法
仮定したレデューサーに、(望遠鏡から出射してきた)F11の光束が入るとして評価。回折を考慮したスポット
を計算しました。波長は400-900nmでST-7/8Eの感度特性を考慮。星像はガイドチップ上の光軸から8mmの位置のもの。
尚、ソフトはFocus Software Inc.のZEMAX-SE (Ver. 9.1) を使用しました。
パラメータ
下図のように、望遠鏡を出た(F11の)光は、図の赤い面で集光するかのように、レデューサーに入射する。
この時のレデューサーの先頭の面から、赤い面までの距離を、物体距離として示した。
実際にはレデューサーで屈折されるため、赤い面では結像せず、その手前の黒い面(CCD面)に結像する。
レデューサーの後ろの面から、黒い面(CCD面)までの距離をバックフォーカスとして示した。
下表のFは、レデューサーに入射する光束がF11の場合のものなので、入射する光束のFが
11からずれた場合には、それに応じてレデューサーから出射する光束のFもずれる。
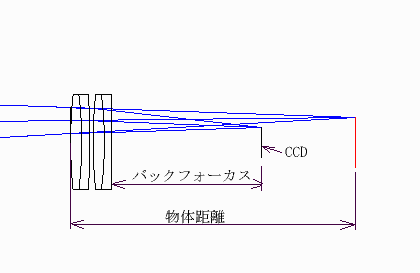
| 物体距離 | バック
フォーカス | F | レデューサ
倍率 | ガイドチップ上の星像 | 図のスケール
(一辺) | 最大強度 |
| 200mm | 95.4mm | 5.9 | 0.54 |  | 73μm | 0.10 |
| 150mm | 79.0mm | 6.7 | 0.61 | 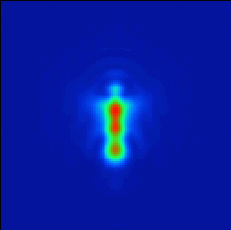 | 83μm | 0.14 |
| 100mm | 57.4mm | 7.8 | 0.71 | 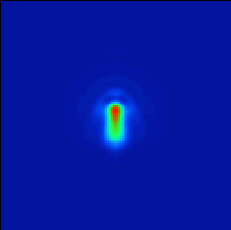 | 96μm | 0.32 |
| 80mm | 46.7mm | 8.3 | 0.75 | 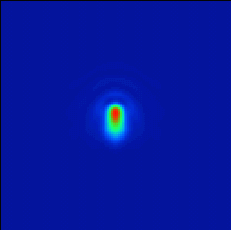 | 102μm | 0.34 |
コメント
この図から判断すると、仮定したタイプ(及び焦点距離)のレデューサーでは、
バックフォーカスを長く(レデューサーで強く縮小)して使用すると
ガイドチップ上の星像が伸びる傾向が見られます(倍率色収差とコマ収差か)。
このため、このタイプ(及び焦点距離)のレデューサーではバックフォーカスを短め(レデューサーであまり縮小しない)に設定することが
ガイドチップ上の星像の観点からは好ましいのではないかと思いました。
(2002/08/28登録)
(2002/08/29追加)
上のレデューサーで、アクロマートレンズが1個(焦点距離が450mm)のみの場合の星像をシミュレートしてみました。
その他の条件は上と同じです。
| 物体距離 | バック
フォーカス | F | レデューサ
倍率 | ガイドチップ上の星像 | 図のスケール
(一辺) | 最大強度 |
| 300mm | 174mm | 6.6 | 0.60 | 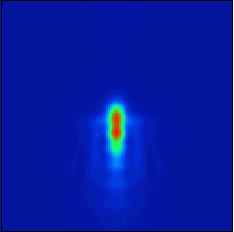 | 81μm | 0.20 |
| 200mm | 133mm | 7.6 | 0.69 | 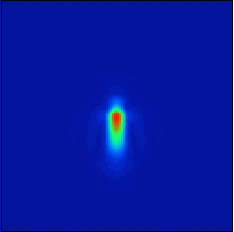 | 94μm | 0.37 |
| 100mm | 76mm | 9.0 | 0.82 | 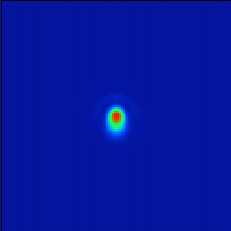 | 111μm | 0.68 |
(2002/08/30追加)
今度は、EDアポクロマート対物レンズ1個(焦点距離が450mm;望遠鏡光学・屈折編に載っていたものを比例倍したもの;2枚分離型)をレデューサーとして流用した場合の星像をシミュレートしてみました。
その他の条件は上と同じです。
| 物体距離 | バック
フォーカス | F | レデューサ
倍率 | ガイドチップ上の星像 | 図のスケール
(一辺) | 最大強度 |
| 300mm | 175mm | 6.6 | 0.60 | 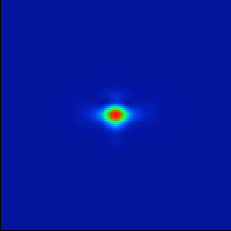 | 81μm | 0.47 |
| 200mm | 133mm | 7.6 | 0.69 | 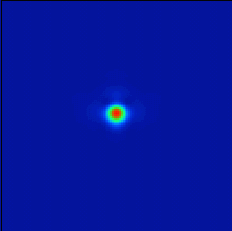 | 94μm | 0.72 |
| 100mm | 76mm | 9.0 | 0.82 | 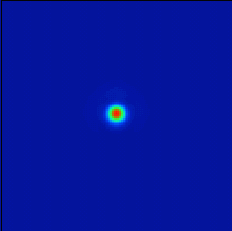 | 111μm | 0.92 |
(2002/09/03補足)
このEDレンズは、望遠鏡光学・屈折編に載っていたF10用の
設計をそのまま使ったため、F6〜8で使う場合には球面収差が出て、
光軸上の性能は、比較したアクロマートよりも悪くなっています。
これはもっと小さなF用に設計されたEDレンズを使えば
改善されるかと思います。
CCDのページへ